骨粗鬆症お役立ち情報
骨粗鬆症を防ぐために必要な栄養素と多く含まれる食品について
骨を丈夫に保つためにはカルシウム、ビタミンD、ビタミンKの摂取が必要です。
骨はカルシウムをためておくタンクのような役割をしています。骨量は18から20歳くらいでピークを迎え、その後徐々に減少していきます。そのため将来的に骨がもろくならないようにするには幼少期にしっかりとカルシウムを摂取し、蓄えておくことが重要です。成年後には骨量は徐々に減少していき、特に女性では閉経とともに急激な減少が始まります。
カルシウムをしっかり摂取することで骨量の減少を緩やかにできる可能性があります。
カルシウムが多く含まれる食品
乳製品
- 牛乳(1杯 200g)
- 220mg
- スキムミルク(20g)
- 220mg
- プロセスチーズ(1切 20g)
- 126mg
- ヨーグルト(1カップ 100g)
- 120mg
- アイスクリーム(1カップ 71g)
- 99mg
魚介類
- 干しエビ(5g)
- 355mg
- ワカサギ(6尾 60g)
- 270mg
- シシャモ(3尾 50g)
- 175mg
- シラス干し(大さじ2 10g)
- 52mg
大豆製品
- 豆腐(半丁 150g)
- 180mg
- 納豆(1パック 50g)
- 45mg
- 生揚げ(1枚 120g)
- 288mg
野菜・海藻類
- 小松菜(1/4束 80g)
- 136mg
- 青梗菜(1株 80g)
- 80mg
- 干しワカメ(50g)
- 39mg
- 切り干し大根(10g)
- 50mg
一日 800mg 程度を目標に摂取するよう心がけましょう
ビタミンDについて
ビタミンDは腸管からカルシウムを吸収する際に必要です。カルシウムを摂取してもビタミンDが足りない状態だとうまく体のなかに取り込むことができません。
ビタミンDは直接食事から摂る以外に、日光(紫外線)にあたることによって皮膚の下で合成されます。このビタミンDは肝臓に運ばれ、貯蔵型ビタミンDとなり肝臓の中に貯蔵されます。その後副甲状腺ホルモンの働きにより腎臓で活性型ビタミンDと変わります。この活性型ビタミンDが腸でのカルシウムの吸収を助けるのです。
このため、肝臓や腎臓の障害がある方でもカルシウムの吸収が不十分となり骨粗鬆症となる可能性があります。
また、ビタミンDは摂取することで筋肉の萎縮を防いだり、高齢者において体のふらつきや転倒を予防したりする効果が知られています。
高齢になって屋内で過ごす時間が増えたり、若者でも日焼けを極端に嫌って紫外線カットをしすぎるとビタミンD不足となる可能性があるため積極的に食事からもビタミンDを摂取するよう心がけましょう。
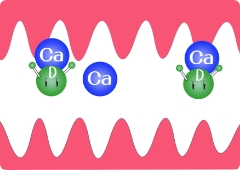
▲ビタミンDがカルシウムを吸収
ビタミンDが多く含まれる食品
魚類
- サケ(1切れ 60g)
- 19.2㎍
- サンマ(1切れ 60g)
- 11.4㎍
- ヒラメ(1切れ 60g)
- 10.8㎍
- カレイ(小1尾 100g)
- 13.0㎍
- シラス干し(大さじ2 10g)
- 6.1㎍
- なまり節(30g)
- 6.3㎍
きのこ類
- きくらげ(1g)
- 4.4㎍
- 干しシイタケ(2個 2g)
- 0.8㎍
一日 5.5㎍ 程度を目標に摂取するよう心がけましょう
ビタミンKについて
骨の強さは骨量(骨密度)+骨質で決まるといわれています。骨の構造をコンクリートに例えると、カルシウムはコンクリートにあたり、骨密度に深い関係があります。
一方コンクリートをささえる鉄筋にあたるのがコラーゲンで、これが骨質に深くかかわっていると考えられています。このためいくらカルシウムが十分に摂れていて骨密度がよくても、ビタミンKが足りなければ骨の強度が保てず、骨折の危険性が高くなってしまいます。骨密度は機械で測定することが可能ですが、骨質は機械で測定することは難しいものです。

ビタミンKはこのうち骨質を高めることで骨を強くする作用があると考えられています。代表的なものでは納豆をよく食べる習慣のある地方では、骨粗鬆症やそれにともなう骨折が少ないことが報告されています。

ビタミンKが多く含まれる食品
野菜類
- ほうれん草(1/4束 80g)
- 216㎍
- 小松菜(1/4束 80g)
- 168㎍
- にら(1/4束 50g)
- 90㎍
- ブロッコリー(1/4束 50g)
- 80㎍
- キャベツ(1枚 50g)
- 39㎍
- サニーレタス(1枚 10g)
- 16㎍
その他
- 納豆(1パック 50g)
- 435㎍
- 卵(1個 50g)
- 7㎍
- カットワカメ(1g)
- 16㎍
- のり(1枚 0.5g)
- 16㎍
- 鶏もも肉(1/2枚 120g)
- 35㎍
一日 150㎍ 程度を目標に摂取するよう心がけましょう
その他の栄養素と摂取を控えたほうがよいものについて
カルシウム、ビタミンD、ビタミンK以外には
- マグネシウム
- マグネシウムは骨の中に貯蔵されるカルシウムの量を調節する働きがあります。
摂取量が少ない場合にはサプリメントなどでの摂取を考慮します。 - ビタミンB6・ビタミンB12・葉酸
- これらの成分はホモシステインという物質の代謝にかかわります。
不足することで血中のホモシステインが増加し、ホモシステイン値が高い状態は骨折の危険因子として知られています。
骨粗鬆症の食事では、エネルギーや栄養素をバランスよく摂取することが大切で、特に避けるべき食品はないとされています。しかし、リンや食塩、カフェイン、アルコールの過剰な摂取は避けたほうがよいと考えられています。
- リン
- カルシウムの吸収を妨げます(加工食品や一部の清涼飲料水など。高齢者の牛乳の摂りすぎにも注意が必要です)
- 食塩
- カルシウムの尿中排泄を促進します
- カフェイン
- カルシウムの吸収を妨げます(コーヒー、紅茶、一部の清涼飲料水など)
- アルコール
- カルシウムの吸収を妨げ、尿中排泄を促進します。また、ビタミンDの働きを妨げる作用があります。
骨粗鬆症の予防に必要な三本柱
「栄養」「運動」「日光」
栄養素として特に大切なのは カルシウム、ビタミンD、ビタミンK の3つです。
運動について
栄養をしっかりとっていても骨への刺激がたりないと骨はもろくなってしまいます。
例えば宇宙ステーションで活躍する宇宙飛行士の骨量(骨密度)は骨粗鬆症患者の約10倍の速さで減少し、半年間の地球飛行を行うと帰還後の回復に3~4年も要すると報告されています。このため骨を丈夫に保つためには適度な運動が必要です。

簡単な運動としては散歩などの有酸素運動(30分以上の持続する運動で、運動の最中にかるく息が上がる程度のもの)が有効とされています。閉経後の骨粗鬆症患者においてウォーキング(8000歩/日 3日以上/週、1年)は腰椎の骨密度を1.71%上昇させたことが報告されています。(山崎ら J Bone Miner Metab 2004)

日光について
ビタミンDはカルシウムを腸から体の中に取り込むのに必要なものですが、食事から摂取する以外に日光(紫外線)にあたることで皮膚の下で作られます。実は日光を浴びて作られるビタミンDの量は食事を通して摂取される量よりも多いといわれており、十分に日光に当たらないとビタミンD不足になってしまう可能性が高くなります。

一日に必要な量としては 夏なら木陰で30分、冬なら手や顔に1時間程度日に当たれば十分とされています。
最近のガラスはUVカットのものが多いため、窓越しの日光浴では十分な効果が得られない場合があります。また、日焼け止めや日傘などを使用しているときも十分な効果がえられません。積極的に日光浴をして骨を丈夫に保つよう心がけましょう。


